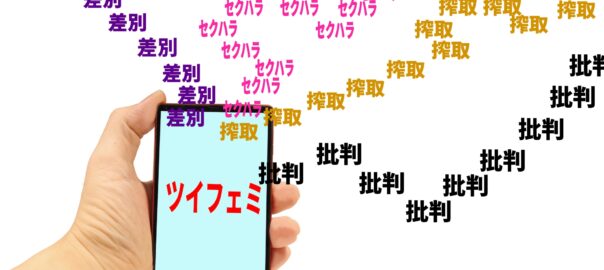日本人はすごいとかそういう動画を目にしたりするわけですが、なるほどおっしゃるとおりと思うものもあったりしますが、バブル前後に欧州で見た光景であったり、未だに高速道路や幹線道路の中央分離帯などを大量のゴミを見ると、積み上げてきたはずのものが結局理解できていないことを目にすることがあります。
日本の公共の場所(含む商店や自宅の前)というのは、かなり奇麗な方であるのは、欧米をめぐってみてもわかることがあると思います。
きわめてゴミが少ない、しかもゴミ箱がないのにと思うのは間違いありません。
1992年のフランスの街角を見た時に、繁華街でこれほど汚いのか(特にタバコの吸い殻でした)とか、有料の公衆トイレの汚さとか「きれいな欧州の街並」なんてのが私の中でガラガラと崩れました。
しかし、今から40年ほど前の日本はと考えると、平気で道路にごみを捨てる人もいましたし、唾を吐く人、タバコをポイ捨てする人など、そこら中にいました。
それに対して「そんなことではいけない」という考え方がでてきて、きれいにしようという活動や、意識づけがあったからこそ現在はゴミが少ない世の中になったのだと理解しています。
少しそれますが、私はルーブル美術館で「民衆を導く自由の女神」が飾ってある部屋に、ドタドタやってきて騒いでいた女性ツアー客の団体を今でも覚えています。
そういう時代から少しずつ公共での立ち位置をどうするかなど、日本人が少しずつ自分たちを律するようになり、それが現在の世界からの日本人の評価になったのだと理解しています。
とても昔からその手の公共の場でのものが優れたなどとは私は思っていません。
◇
さて、細かいことでいうと、拙宅の前は駐車場となっており、明確に私有地と行動が縁石で分けられているわけですが、無断で立ち入る人が多くなったため、大家さんと相談してチェーンで仕切ることにしました。
しかも私有地側の協会には丁寧に「立入禁止」のボードまで貼り付けてある状態です。
なぜここまでやるようになったかと言えば、特に夏場に日陰を求めて家の玄関の前まで入ってくる人などがいるからなのですが、一部の方は入ってきたうえに置いてある植物を荒らしたり、大家さんの自宅側のエアコンの室外機に座って足を壊したり、果ては玄関を開けたら目の前に人がいるなどという状況になったからこそ明確にチェーンで仕切ったわけです。
ところが、それを無視して入ってくる方々や、わざわざ立入禁止と書いてあるボードを踏んでチェーンに触った状態で立っている人、果てはチェーンをかけているポールを動かす始末です。
九割の方はそのサインを守っていただけるわけですが、残りの一割がこんな非常識なことをするわけです。
駐車場でいたずらをされないように防犯カメラを設置しているわけですが、そんな非常識なことをする人たちが50人以上いるというなんとも情けない状態なのです。
残念ながらお年を召した方もいるわけで、その非常識さに悲しくなります。
せっかく公共での立ち位置とか姿勢とか、日本人はまともだと思われているはずなのに、残念ながらそういう方がまだまだいて、それが残念ながら増えている印象です。
エコノミックアニマルと呼ばれていた時代を知らない人からすると、その蔑称を払拭するために動いた世代が公共でのことを考えたわけで、だからこその今の評価となっていると思うのですが、残念ながらその意思は継がれることなく「私は日本人だから世界では・・・」などと勘違いをして、行動している人が増えてきているのではないかと予想しています。
そして、まともなことをしない人(ルールを守れない人)ほど、ガチャガチャ言っているようにしか見えず(わきまえないなんちゃら的なやつも含めね)、まともなことであったり、ならぬことはならぬという日本語を理解できないのだなと感じています。
だからこそPTAで子供たちと真剣に接して、うるさいと思われようと正しいことを話してきて、ようやく周りはだいぶ理解してくれましたが、ほんとうに微々たるもので・・・