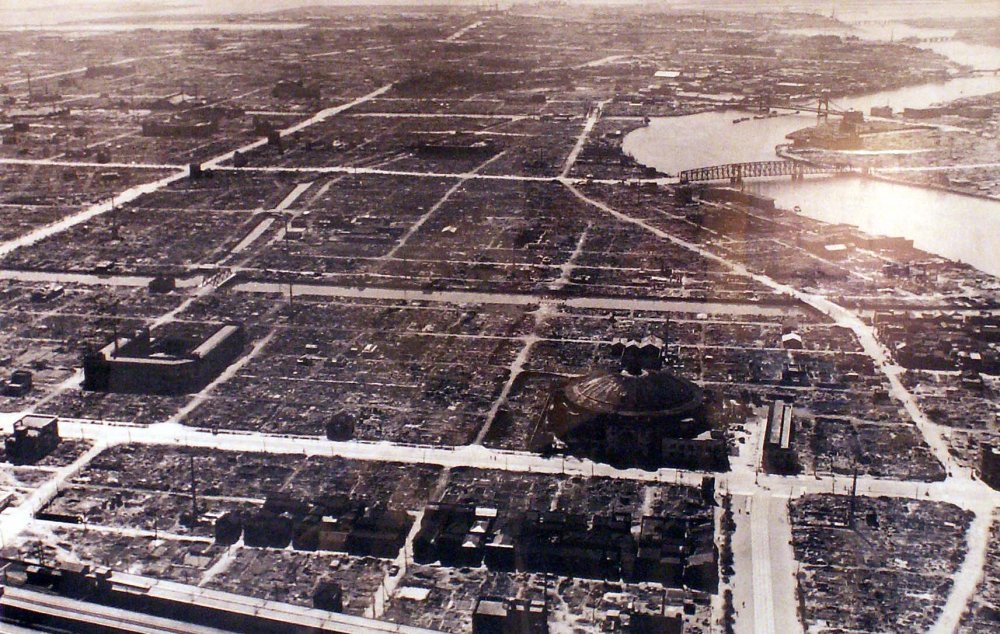アジアのエリートは、なぜ日本企業で働きたくないのか?グローバル・ビジネスリーダーの育成と活用【第5回】(Diamond Harbard Business Online)
日本企業の人気が落ちているそうで、その理由について考えてみた。
人気がない理由は以下で、日本企業に働いたことがある人ほど、より働きたくないと答えているそうだ。
・給与や昇進が年齢や勤続年数で決まる。
→これには賛成。マネジメント能力で昇進がきまるべきだし、給与は職能であるべきだと思っている。ただし、それをどう数値化するのかというのはどこの国でも悩むところなんですがね。
・規則が多すぎる。
→これも多いと感じますね。しかし、海外企業の場合は就業に関しての契約が膨大で、そちらと比較した場合実は日本企業は少ないんじゃないの?と感じますよ。
・キャリアパスが見えない。
→これは一番目とかぶっていることで、結局サラリーマンとしては昇進と昇給しか興味がないわけですから、それをはっきりした形で道をつくってあげなければならないでしょう。
・ローカルスタッフを尊重しない。
→そんなことはない会社をいくつかしっています。
・マネジメントポジションが日本人で占められる。
→これまたそんなことはない会社をいくつかしっています。そして海外企業がローカルスタッフをそんなに尊重するかと言えば、そこまで尊重されていませんが昇進などに関してうまくやっているなという印象です。
・現場での改善活動を行っても、それが当然とされ、評価してくれない。
→これに関しては同じ考え方で、改善することをもっと評価する必要があると感じます。
・職場でのプレッシャーが大きい。
→なにがプレッシャーなの???とサラリーマンではない私が言ってみる(苦笑)
・時間管理が厳しい。
→日本の会社の時間については厳しいかもしれませんが、意外にホワイトカラーの現場はそうでもなかったりするので笑ってしまいます。現場レベルで時間管理が厳しいのは、実はドイツの工場なんかもそうだったりするわけで、それはそれぞれの国の考え方によるものだと思っています。
・少しのミスも許されない。
→これに関しては当てはまる部分があると思いますが、もう少し失敗に寛容になってもいいとは思います。
・残業、長時間労働が評価され、効率的な働き方が評価されない。
→これに関しては全面的に賛成。定時に帰ってきちんと仕事をこなしているのに、なんで白い目で見られるのかわかりません。ある現場で「なぜ定時に帰ろうとするのですか?」と聞かれ「当たり前でしょ。まして全部納期通り以上にやっているのに何の問題があるの?」と聞き返してクビになったことがあります(笑)まあ、そんなところは仕事をしたくありませんがね。
・仕事が多い割に給与が低い。
→どうなんでしょうね・・・ただし、最低給与をきちんと保証されるし、仕事があまりできなくとも正社員であれば身分を保証されるのでなんとも言えないでしょう。上昇志向の人であれば、そんなところにはいないリスクの高い職場がいいでしょうね。
・日本人はいつも日本式のやり方を押し付ける。
→これも一部のような気がするわけです。
ってことで、これをみて思ったのはいわゆる「外資」のハイリスク・ハイリターン構造を好んでいるというのが見て取れるわけですが、うまくいけばハッピーなあの世界も、いちど落ちてしまうととてつもなく深い泥沼だということを理解した方がいいでしょう。
そして、このアンケートに回答したであろう人達は、上昇志向の人達であって、日本人のように「平均がいい」という人たちではないというところに気が付きます。
ということは、自分の能力を高いと思っているわけですからハイリスク・ハイリターンでいいのです。
いろいろなところで仕事をさせてもらって、某自動車会社の東南アジア系ローカルスタッフの優秀さとその肩書き(当然マネージャークラスです)に驚くこともありますし、素晴らしい人たちを多く知っていますが、その反面というか工場のローカルスタッフは目を離すとサボろうとするという二極化状態であるのもまた事実です。
日本人のようにあるいみ平均的なものを持っている状態ではないため、当然ながら給与格差は広がりますし、それは日本以上だということです。
昨今、日本の一部で貧困が話題になっているようですが、日本の貧困は彼らの比では全くありませんし、日本の場合はある意味努力で何とかなるケースが多く見られます。
当然、救わなければならない家庭などもあるわけですが、残念ながらその貧困の責任が自分にあるということを理解したとしても、その考えを努力に結び付けられない人もいます。
・・・と、最後は国内の方になってしまいました^^;